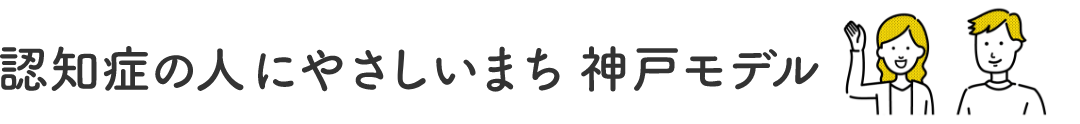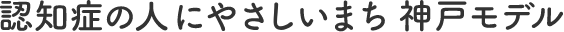よくあるご質問
認知症の人にやさしいまち『神戸モデル』の認知症診断助成制度・事故救済制度に関連するよくお問い合わせいただく内容です。
- 問1: 認知症診断助成制度について、費用はいくらかかるのですか。
- 答え:
65歳以上の方は、第1段階、第2段階とも自己負担なしで受診できます。
※第1段階は無料ですが、受診券(あらかじめ市に申込み)が必要です。
※第2段階は保険診療なので一旦窓口で自己負担分を支払っていただきます。後日、神戸市に申請いただけば、助成金として検査に係った金額をご指定の口座に振り込みます(償還払い。振り込みまでおよそ3~4ヶ月程度)。一旦お支払いいただく自己負担額については、本人の医療費負担割合や、必要な検査により金額に幅(数千円~数万円)があります。
- 問2: 認知症診断助成制度の受診時の注意点はありますか。
- 答え:
予約制の医療機関があります。
認知機能検診、認知機能精密検査とも必ず、電話で医療機関と相談のうえ受診してください。
(持ち物)認知機能検診:受診券<認知機能精密検査:健康保険証、福祉医療受給者証
(お持ちの方)、認知機能精密検査依頼書(紹介状に相当するもの)。 ※認知機能精密検査依頼書は認知機能検診を受診した医療機関から封筒に入れてお渡しします(開封厳禁)。
※生活保護を受給されている方は、受診前に担当のケースワーカーにご相談ください。
- 問3: 認知機能検診の受診券を忘れた場合や無くした場合はどうすればいいですか。
- 答え:
受診券を忘れた場合は、受診券を持参したうえで受診しなおしてください。
受診券を無くした場合は、再発行します。通常の受診券申込と同様にお申込みください。
約2週間で受診券を送付します。申込方法は下記URLをご確認ください。
https://kobe-ninchisho.jp/dementia-diagnosis-subsidy-system/#before-examination
- 問4: 認知症事故救済制度とはどういうものですか。
- 答え:
認知症事故救済制度は、認知症と診断された方を対象に、
①賠償責任保険に市が加入
②事故があった際に24時間365日相談可能なコールセンターの設置
③所在が分からなくなった際のかけつけサービスを含むGPSの導入費用の負担を実施するとともに
④認知症の方の起こした事故に遭われた全ての市民に見舞金(給付金)を支給するものです。
- 問5: 賠償責任保険と見舞金(給付金)の違いを教えてください。
- 答え:
償責任保険も見舞金も、認知症の人が起こした事故に対して給付されるものです。
賠償責任保険は、保険金が支払われるためには、認知症の方があらかじめ市に申込みをする必要があります。また、保険加入者が事故を起こした際、その方に賠償責任がなければ、保険金は支給されません。
一方、見舞金(給付金)は、事前に申込みをする必要はなく、認知症の人が起こした事故であれば、賠償責任の有無にかかわらず、見舞金(給付金)が支給されます。 ※認知症と診断されていない方が事故を起こした場合についても、支給対象になる場合があるため、事故が起こった際は事故救済制度コールセンター(0120-259315)へお電話ください。
(神戸市が指定する医療機関(認知症疾患医療センター)において、事故当時既に認知症であったと診断された場合に対象となりえます。実際の支給についての判断は、事例により個々に行いますので支給対象外となる場合もあります。)
その他のご質問については神戸市のFAQをご覧下さい。